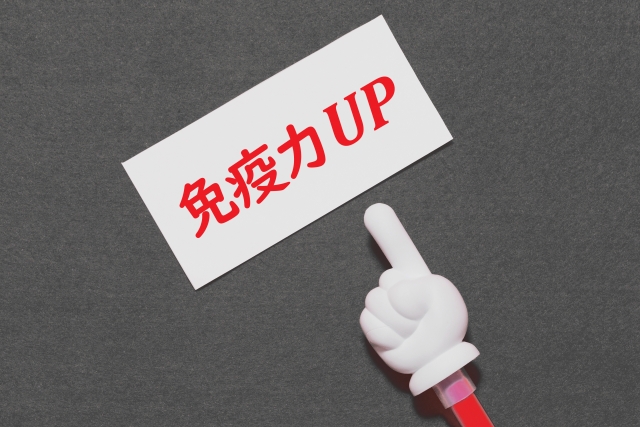こんにちは。 浜松市・豊橋市の パーソナルトレーニング・コンディショニング専門店 S-pace【エスペース】です。 今回のコラムは『筋トレで糖尿病悪化を防ぐ』についてです。 はじめに 糖尿病 […]
タグ: 高血糖
糖尿病患者のがんのリスク
こんにちは。 浜松市・豊橋市の パーソナルトレーニング・コンディショニング専門店 S-pace【エスペース】です。 今回のコラムは『糖尿病とがんの関係』についてです。 日本人の […]
血糖値が継続して高い!これって糖尿病予備軍?
こんにちは。 浜松市・豊橋市の パーソナルトレーニング・コンディショニング専門店 S-pace【エスペース】です。 今回のコラムは『糖尿病予備軍』についてです。 生活の欧米化 […]
えっ!?高血糖だと感染症のリスクが上がる原因
こんにちは。 浜松市・豊橋市の パーソナルトレーニング・コンディショニング専門店 S-pace【エスペース】です。 今回のコラムは『糖尿病と免疫力の関係』についてです。 糖尿 […]
あなたが糖尿病にかかる確率が分かっちゃう○×問題
こんにちは。 浜松市・豊橋市の パーソナルトレーニング・ コンディショニング専門店 S-pace【エスペース】です。 今回のコラムは 最近血糖値が高いと感じる方や […]